こんにちは、原田です。
先日、U15女子チームで指導を行いました。
(「勉強会」という名前で直接指導を行っています)
大和籠球のコミュニティメンバーの方が指導しているチームで、
前から僕のYoutubeを見て、Princeton Offenseの「Chin」を導入されていたり、
バックカットを軸にした面白いオフェンスをしているチームです。
今回のテーマは「ディフェンス」「基礎」でした。
目次
「賢者は強者に優る」を実現するために
大和籠球では、Princeton Offenseを軸とし、
Princeton Offenseの創始者「Pete Carrilさんの哲学」を理念としています。
その一つが「賢者は強者に優る」というもの。
これはPete Carrilさんが小さい頃から、父親に言われていたことで、
より正確には、
「この人生において、強い者は弱い者を支配している。しかし、賢い者は強い者をも支配できる」
という台詞になります。
この言葉は、とても理想的に思えるものですが、
実際にそれを実現したのがプリンストン大学、Pete Carrilさんです。
僕らはPete Carrilさんの原文を正しく受け取り、自分なりに解釈して、現場(リアル)に落とし込んでいく必要があります。
原文はこうなっています。
「The smart take from the strong」
知性や戦略で賢く戦うことで、自分達よりも強いチームから勝利を得ることができる。
僕はプリンストンを10年近く学び、
自分でプレーし、それを学生チームに伝え、ネットで配信をして、
「賢者は強者に優る」を実現できるようなバスケのモデルを伝えています。
ただし、これは簡単なことではありません。
強いチームに勝つ、というのは。
所謂「ジャイアントキリング」になるわけですが、
そのためには、賢さの中に「強さ」をもたないといけないと感じています。
また、Pete Carrilさんの哲学を学ぶと(書籍『賢者は強者に優る』)、
この言葉は単にバスケットボールの話だけではなく、「人生においても」重要で、
常に学び、賢くあることで、バスケットボールを通して自分自身を成長させていくことに繋がります。
そんなバスケットボールを伝えていきたいと思っています。
で、
スポーツにおいて「勝つ」ためには何が必要か?
その視点で、僕は勉強会(直接指導)をしているのですが、
Princeton Offenseの細かい動きやコツの”前に”いつも伝えていることがあります。
それが「基礎」です。
ここでいう基礎とは、
・ボールを簡単に失わない技術
・ボールを確実に繋いでいく技術
・ドリブル、パス、シュートの基礎技術
のことです。
そして、勝つためには「ディフェンス」の強化が必要。
オフェンスは楽しいし、バックカットは面白いし、Princeton Offenseは自由でたくさんの可能性があります。
でも、実際に試合で勝つためには、
やっぱり「ディフェンス」と「リバウンド」なんですよね。
今回はそんな視点で、チームの状況を見て、一番必要だと思われる「基礎」「ディフェンス」を指導しました。
ボールハンドリングの重要性
ボールハンドリングの基礎、ドリブルの基礎など。
スラムダンクの桜木がやっていた「ボール回し」というハンドリング練習、
僕はこれを中学生~高校生の間、毎日必ずやっていました。
全力で、家の中で。
毎日3分でもいいので、とにかく継続しました。
「今日は面倒だなぁ」と思える時も、
「毎日やると決めたからやる」と1分でもとにかく継続。
ただやるのではなく、全力でやると決めて、スピードを上げてやっていました。
このボール回しというハンドリングは、古典的だし、
実際の試合でこれと同じ動きがあるか?と言われれば無いです。
(レイアップに行くときにボールを隠すおしゃれプレーであるくらい)
でも、これを本気でやると
・指先の力
・腕周りの必要な筋力
・低い姿勢、低い重心
・手を速く動かす力
・ボールの中心を捉える力
などが身に付きます。
特に「足回り」はとても大切だと思っています。
この低い姿勢をキープしながら、手を速く動かす。
ドリブルでもシュートでも、
ボールを扱う時に指先でコントロールする必要があります。
ボールの中心を捉えることで、少ない力で大きな成果を出せます。
そういった基礎を身に付ける上で、こういうハンドリング練習は効果的だと僕は考えています。
また、これで身に付けたいのは、
・自分一人で自分を上手くする習慣
です。
つまり、自主練の習慣。
始めは、ドリブル練習から入るといいと思っています。
その延長線上に「シュート」「パス」があり、チームバスケがあります。
まずは、自分のために。
自分一人で出来る練習を。
「習慣が人生を創る」
という言葉がありますが、
これは本当だと、最近ひしひし感じます。
バスケを上達させたいなら「良い習慣を取り入れる」が大切。
習慣とは、継続すること。
どんな小さなことでも「継続」すると、やがて大きな差を生みます。
本当に。
でも、どんなに良いことを学んでも継続しなければモノになりません。
「身に付かない」ということは、つまり「使えない」ということ。
このボール回しと言うハンドリング練習は、とても古典的で地味ですが、
でも、継続することで確実に「力」になります。
ドリブル、パス、シュート、すべてに通じます。
「ボールハンドリング(ボールを扱う技術)」ですからね。
そんなハンドリングを実践した後は、パスの基礎などを伝えました。
パスの重要性
ハンドリング、ドリブルの次は「パス」について。
パスはPete Carrilさんも、とても大切にしていたことです。
・「パスを使え」
『賢者は強者に優る』p31
パスは長年にわたり、チームの武器になっている。私がシューターと同様にパッサーが好きなのは、誰にでも決めることができるショットをセットアップできるからだ。チームのすべての選手がパスに関わるのを見ることは気分が良いものである。
オープン選手を察知できるパッサーは、いつ、何処でスクリーンをかけるか、ピックを防ぐか、ディフェンス側に有利となるかを認識できる能力を備えている。言い換えれば視野の広い選手であり、ウィークポイントは何か、ドライブは何処か、そしてコートの何処に誰がいるかを把握できる選手である。彼はその情報に基づいてボールを移動する。彼こそが我々のチームの最大の武器となるのである。ポイントを得るには、ボールを動かさなくてはならない。我々は、ディフェンスを動かすためにパスをし、あらゆるパスが価値を持つ。あるパスはポイントを生み、他は何かのきっかけとなり、そのきっかけはパスによって生じる。パスによる攻撃は次のステップを容易にし、次のパスは更なる攻撃の手助けになる。反対に、まずいパスによって始められたオフェンスは、次のパスを困難にし、最終的にはボールを失わせるのである。
私がパスを好むもう1つの理由は、チームのモラルをはぐくむことができるからである。パスは受け取ることによってお互いの信頼感を築くことができ、ゲームでの不必要な緊張感を解きほぐすことができる。また、パスは各選手がチームの一員としてゲームを組み立てていることを自覚させる効果を持つ。
パスには必要となる2つの根本的な要素がある。1つは、パスをすることを求めて、その価値を認識することである。これは教えることが可能である。次は、オープン選手を読み取る能力である。私にはこれは教えることが不可能であった。すべての偉大な選手はこの能力に非常に長けている。
単にオープン選手を読み取る能力以上のことが関わってくる。偉大なパッサーはオープン選手を読み取った上に、パスを出した後にチームメイトがどのように対応するかをも読み取る。良いパッサーは、パス後にプレーの展開を見ているが、偉大なパッサーは、パス後の結果が明らかにチームに不利な展開になると予測すれば、そのパスを避けるであろう。さらに偉大な選手のパスは、キャッチしやすいボールでもある。
パスほど良いチーム作りに貢献できるものは存在せず、逆に決してパスをしないシューターほどチームの雰囲気を壊すものはない。
・・・
選手は、パスの正確性や創造性の価値を理解する必要がある。ゴールから18フィート[約5.49m]の距離にいるチームのベストシューターがオープンとなり、チームメイトが彼の膝元にボールをパスしたとすれば、それは良い選手とは言えない。パスの正確性が非常に重要となる。あまりに低いパスは、ミスショットを招く。パスを胸の位置へ送れば、すかさずショットが打てるのである。これはとても重要なことだ。パスされたボールをどこでキャッチするのかを軽視する偉大なコーチもいるが、私は違う。小さな積み重ねこそがチームを勝利へ導くことは言うまでもない。
パスは、近代のバスケットボールゲームが失ってしまった芸術ではないだろうか。私は、ハイスクールのバスケットボールクリニックやキャンプに呼ばれた際には、パスの価値を強調するために熱心に指導する。時に私を失望させるのは、75%ものハイスクールの選手がオープン選手にパスを送らないことである。これは、傲慢さの表れである。身動きができなくなった時だけ、パスをする選手が多すぎる。それはパスではない。
プリンストンを伝える発信者として、やっぱり、この「Pete Carrilさんの哲学」をちゃんと伝えたい。
伝えなければいけない、と思っています。
パス、とても重要ですよね。
そのパスの効果、意味、価値を
Pete Carrilさんが言語化してくれています。
上記の文章、飛ばさず、読んでくださいね。
指導者の方であれば。
そんなパスの価値を高めるために、
今回は一つにポイントを絞って
・パスの強さと丁寧さ
を伝えました。
これだけ、でいいと思っています。まずは。
今は「チェストパスは試合で使う場面が少ないからワンハンドプッシュパスで」という指導が一般的ですが、
僕は、チェストパスを丁寧に、良い姿勢で、正確に、強く出せるように訓練することをまず最初にやるべきだと考えています。
もちろん、ワンハンドプッシュパスも、ボックスの外(ディフェンスの手に当たらない位置)からのパスも重要です。
でも、その前にまずは普通のパスを確実に出せるように。
パスが出せない選手は非常に多いです。
ここでいう「パス」とは、Pete Carrilさんが言う「パス」です。
Carrilさんはこう言っていますよね。
パスは、近代のバスケットボールゲームが失ってしまった芸術ではないだろうか。私は、ハイスクールのバスケットボールクリニックやキャンプに呼ばれた際には、パスの価値を強調するために熱心に指導する。時に私を失望させるのは、75%ものハイスクールの選手がオープン選手にパスを送らないことである。これは、傲慢さの表れである。身動きができなくなった時だけ、パスをする選手が多すぎる。それはパスではない。
僕も昔はそんなプレイヤーでした。
1対1だけを考え、1対1が止められたらパスを出す。
でも、それは「パス」ではないわけです。
まさしく、Carrilさんの言う通り。
そして、ドリブルと1対1が最盛期の今、
そういった選手が増えているのも事実ではないでしょうか。
パスの楽しさを覚えられるとバスケの世界が変わります。
別の競技をしているんじゃないか?くらい変わります。ほんとです。
学生時代に、僕がパスの大切さを知らなかったからこそ、
今、直接指導ではこのパスの大切さを学生たちに伝えていきたい。
バックカットと合わせて。
大和籠球の軸として「バックカット」がありますが、
バックカットは一人で成功させられるものではありません。
必ず、仲間の協力が必要です。
そこには「パス」があります。
パスは味方を繋ぐものだし、
チームで相手を崩すものです。
パスの価値に気付けると、視野が広がります。
「バスケットボール=人生」なので、
パスの楽しさや価値に気付いて視野が広がると、
それは結果的に、人間的な視座を高めることにも繋がるでしょう。
ディフェンスの3原則と姿勢の重要性
今回のメインテーマは、ディフェンスでした。
・ポジショニング
・どうやって予測するか
・ディフェンスの正しい姿勢
・フットワークの練習方法
・手の使い方、上げ方
・1線の間合い
・スティールの仕方
・ディナイの間合いと目線
など
今回指導したのがU15のチームで、初心者の子もいたので、
チーム全体に向けて「基礎を一から丁寧に伝える」をしました。
※練習開始前に「ディフェンスの三原則」について解説しました
多くの人が曖昧にしている「自分にとって一番いいディフェンススタンス」について。
良い姿勢で100時間練習するのと、
悪い姿勢で100時間練習するのでは、
当然、成果は変わります。
じゃあ、その「良い姿勢」って何なのか?
それが曖昧だから、曖昧な状態が積み重なってしまいます。
大和籠球では、「自分にとっての正しさ」というのを「対人チェック法」を使って見つけます。
この「検証法」があるから、
自分の外側に答えを求めることなく、
自分自身の内側に目を向けられるようになります。
「人から言われたこと」「本に書かれていること」「動画で有名なコーチが言っていること」
それらは本当の答えではなく、一つの視点なだけです。
参考にするのは良いですが、妄信するのは違います。
そうしてしまうと、自分自身を見失ってしまいますし、
いつまでも自分の外側に答えを求める人生になってしまいます。
自分自身の在り方は、対人を通してしか分かりません。
人と関わる中で、自分の在り方が分かります。
自分の課題も良さも個性も、相手を通して分かるもの。
この世の中は相対関係で成り立っています。
例えば、
「頭が良い」というのも、
何を基準に、何と比較するかで変わりますよね。
「テストの点数が高い」という指標なら「賢い」かもしれないけれど、
東大生の中に入ったら「賢くない」にほとんどの人はなります。
自分の良さも課題も、個性も、
対人で人と関わる中で相手から教えてもらったり、
相手と関わる中で「あ、自分っていうところがあるな」と氣付けるもの。
バスケットボールも一緒です。
人と関わることで自分の状態が分かります。
ディフェンス練習においては、
自分にとっての良い姿勢を対人チェック法で見つけ、
その状態をキープできるようにフットワークを構築していきます。
大和籠球では、ディフェンスフットワークの順番として
1.接触あり
2.接触なし
を推奨しています。
多くのディフェンスフットワークは「2.接触なし」からスタートします。
でも、そうすると、必要以上に動いてしまうことがあります。
つまり、オーバーディフェンスになりやすいという事です。
フェイクにも過剰に反応してしまうようになります。
逆に、接触ありから練習すると、正確に相手の位置に合わせたフットワークが自然と身に付きます。
物理的に触れているので、
相手とのズレを正確に認識できます。
「相手が動いた分だけ動く」
これを無駄のないフットワークだと定義すると、
非接触では分かりにくいことを、誰でも明確に分かります。
また、接触から行うと「自分の癖」も見えてきます。
相手に押させて自分の足を動かすフットワークをしていると、
身体は”自然な反応”を起こします。
例えば、相手に前から押されている時、
人間の自然な反応としては「一歩ずつ後ろに下がる(後ろに歩くように)」となるのですが、
これは一般的に指導されている「ジャンプしながら両足で後ろに下がる」というフットワークではありません。
・自然な動き=無駄がない=無意識にできる=相手に付いていきやすい、疲れにくい
と言えるので、できる限り「自然な動き」を僕らは身に付けるべきです。
この後ろに下がるフットワークに関して言えば、
一般的に言われている「小さなジャンプをして後ろに下がる」をすると、
その瞬間、相手に反応されたら付いていけない、ということが分かります。
ここでは中学生に伝わるように大げさにジャンプしていますが、
実際にこれをして守ろうとすると、こういう現象が起きているという事です。
接触ありからディフェンスフットワークを行うと、そういったメリットがあり、
正確なフットワークを身に付けた後に、非接触のディフェンスフットワークをするといいです。
その際、接触から練習しているので、身体に「接触感覚」が残っています。
その接触感覚を思い出しながら行うと、
非接触でもより正確に相手に付いていけるようになります。
これが正確で確実なディフェンスフットワークを身に付ける手順です。
もちろん、足腰を鍛えるためのフットワークも重要なので、
そういった目的で行う厳しい激しい練習が悪いと言いたいわけではありません。
ただ、「正確なフットワーク」というのを明確に指導者が理解して、指導できるようになる必要があると思っています。
それを誰でも指導できるような仕組みが「大和籠球」です。
・対人で行うこと
・接触ありから行うこと
・自然な動きと自分の癖に気付くこと
これがとても大切です。
その先に「チームディフェンス」があり、
一人ひとりの正確なディフェンス力を高めることができたら、
チームのディフェンス力は更に高まるのは言うまでもありません。
是非、このディフェンスフットワークを”継続”してやってみてください。
オンボールディフェンスの間合いと手の使い方
大和籠球の勉強会では、はじめに「得たい成果」を学生から聞いています。
・今日の練習で「得たい成果」は何ですか?
というシンプルな質問。
シンプルですが、選手の主体性を引き出し、練習の吸収力を高めるために非常に重要な問いかけです。
(詳しくは、こちらの記事をご覧ください)
今回、その得たい成果の中に
・1線(ボールマンのディフェンス)の間合いとハンズアップの仕方
というのがありました。
ディフェンスの姿勢とフットワークを正確に身に付けた後は、「対人での1対1」をしていく必要があります。
今回は学生からの得たい成果に合わせて、
・1線の間合い
・ハンズアップの仕方
を伝えました。
まずは、シュートチェックの考え方について。
多くの選手は「シュートの終わり」から止めようとして、バランスが悪い姿勢になっています。
手を上げすぎて、抜かれやすい姿勢になっています。
シュートチェックは良いディフェンスのために必須です。
でも、その結果、抜かれすぎてしまう状態になったら良くないので、
僕は「シュートの始まり」を止めるように、まず手の使い方を指導しています。
シュートの終わりを止めようとすると、必要以上にジャンプしてしまったり、間合いが遠くなります。
でも、「シュートの始まりを止める」ということを基準にすると、
自然と間合いは近くなり、相手のシュートフェイクにも反応しすぎなくなります。
その結果、間合いが良くなります。
この時、先ほど話した「自分にとってのいい姿勢」を知っておく必要があります。
そうでないと、こういった対人練習(1対1や3対3)の際、
「自分が乱れた時に良い状態に戻せない」ということが起きてしまいます。
「自分にとってのいい姿勢が曖昧だと、曖昧な技術が積み重なってしまう」
基本の間合いとフットワークを身に付けた後は、
「よくある相手の攻めに対する守り方」を練習しました。
ここでは時間の関係もあったので、「スティールの基礎」を伝えました。
「シュートの始まりを止める」
この発想で、オンボールディフェンスは向上します。
◆イグドラのスティール「swipe down」
— 原田毅@NBAで凄いのはダンクだけ!? (@nbanotdankudake) September 29, 2024
「シュートの始まりを防ぐ」
ブロックに飛ぶことも大切。コンテストすることで相手のリズムを崩す。でも、その前にシュートの始まりを防げたらベスト。
手を隠して相手のキャッチの瞬間を狙う、身長の低い選手は特に必要な技術。pic.twitter.com/ZizysvIVKO
あとはこの理論を身に付けるための練習ドリルを実践しました。
ディナイの間合いとオフボールのポジショニング
次に、オフボールのディフェンスについて。
「ディフェンスの三原則」の第一は、ポジショニングです。
正確なポジショニングを取らなければ、すべての反応が遅れてしまいます。
「ビジョン」も悪いので、味方に声を出して、チームで守ることも難しくなります。
まずはポジショニング。
じゃあ、その「正しいポジショングってどこなのか?」という基準を今回は伝えました。
今回はチームの状況・課題を見て、
・2線のポジショニング
・ディナイ
を指導する必要があると感じたので、そこを重点的に。
まず、2線の「準備」と「予測」について。
ギャップポジション(ドライブを止めるポジション)に入るのは、相手がドライブをして来ようとしているorドライブが脅威な時。
そうではない時は、そのポジションにいる必要はなく、
ボールマンの状況を読んでポジショニングを細かく変える必要があります。
その理論を説明して、実践。
2線のポジショングを考える時、
・ギャップポジション
・ディナイポジション
をどう定義して、どう使い分けるかを、チームで決める必要があります。
今回指導したチームは、
・ギャップポジションは取れているけれど、簡単にパスを回されている
という課題があったので、ディナイの間合いを伝えました。
ディナイは一般的には手を見せて、パスを遮断(deny)します。
そもそも、パスを出させない、という守りです。
でも、これはバックカットが上手いチームであればバックカットされてしまうし、
相手がバックカットを練習してなくても、自然と相手から”バックカットを引き出してしまう”ということが起きます。
特に相手が強ければ強いほど、そうやって攻められるので自分たちが不利になります。
「賢者は強者に優る」を実現するために、
賢く戦うには「ディナイの間合い」を改めることをお勧めしています。
まずは間合い。
パスカットも出来るし、
バックカットにも反応できる。
ドライブに対しても反応できる。
・・・という、
理想に聞こえるかもしれませんが、
すべてに対して反応できる間合いを取ります。
これは言葉を変えると「ニュートラルな位置」です。
オーバーディフェンスをしていない、
自分達主体で守っている状態と言えます。
大和籠球では、この正確な位置を「目線」で調整するように伝えています。
一般的には、「ピストルスタンス」といって「指をさすこと」で良いポジショニングを意識するように指導されます。
これは初期段階としては必要な指導であるし、
ハンズアップも守るためには大事ではあるのですが、
ただ、「手を挙げることが目的になってしまう」という現象が起きることがあります。
つまり、これを「手段の目的化」と言います。
手段の目的化は、スポーツ指導においてもですし、
仕事や何かを学習する際にも、人生でも起きやすいことです。
注意しなければいけません。
本来は手段であるはずの「マークマンとボールマンの両方を指さす(視野に入っているかを確認する)」ということが目的になると、
本来の目的である「相手を守る」「次のプレーを予測して素早く反応する」ということがなおざりになってしまうことがあります。
ピストルスタンスを身に付けて、ある程度の基礎が身に付いたら、一度それは「捨ててもいい」と僕は考えています。
選手はプレー中、コート上で多くのことは意識できないので、
出来る限り、考えることは少なくした方が成果に繋がりやすいからです。
そんなポジショニングの意識を伝えた後、「ディナイの間合い」について話しました。
間合いを詰めすぎると、簡単にバックカットをされる。
間合いを空けすぎると、簡単にパスを出される。
その「中間の間合い」をとることを推奨しています。
これは僕もプレイヤーとして実践しているのですが、
とても効果的だし、ディフェンスが更に楽しくなります。
そして、ディナイの際、「手を見せない」というのもポイントの一つ。
これをすると、ボールマンは油断して緩いパスを出してくることがあります。
(実際、大学生を指導していた時、これでスティールが増えました)
手を出していると、ボールマンはその手に当たらないようなパスを出してきます。
考えずとも、自然とそういう風になります。
でも、手を隠していると、
「パスが出せそうで取られそう」
という、相手は迷いや考える時間が生まれます。
そうなると、プレーが少し遅れるし、自分たちが少しでも優位な状態を作れます。
「パスを出させないようにフルディナイする」
「ディナイをしてバックカットを引き出して3線が守る」
という、積極的なディフェンスもあります。
それはそれで強いですし、勝つためには必要だと思います。
でも、そういったディフェンスを最初からただ闇雲にやるだけだと、
「正しいポジショング」「正しい判断」ができなくなってしまいます。
応用は基礎ができた後。
その基礎とは、
・ニュートラルなポジショニングをとって、予測しながら反応する
です。
まずはそこを身に付け、その後にチームのカラーを入れていってほしいと思います。
この間合いが取れるようになると、
「パスを出させて取る」ができるようになります。
◆スティールのコツ
— 原田毅@NBAで凄いのはダンクだけ!? (@nbanotdankudake) October 23, 2022
「手を隠す」
これは実際に大学生を指導していた時に教えていたことで、かなりスティールの数が増えた守り方。
あらかじめ手を出しておく(見せておく)と、相手の警戒心が高まる。隠しておくと氣が緩む。
ハンズアップが全てではないpic.twitter.com/fSctko8w4y
これができるようになると、ディナイの質は大きく変わります。
しかも、これはとても楽しいです。
「駆け引き」の楽しさを伝えたいという想いも、大和籠球の中に含まれていて、
それはバックカットだけではなく、「ディフェンス」でも伝えていきたいと思っていることです。
そんなディナイの間合いとスティールの練習もして、あとは対人。
練習最後は、学生たちで振り返り。
今回は午前中のみの指導になりましたが、
数時間で選手たちは成長を感じられていたようで何よりです。
大和籠球は、日々、現場の指導者と選手と関わりながら進化しています。
「賢者は強者に優る」を実現するための教科書として、
プリンストンとPete Carrilさんの信念を進化発展させていきます。
「お辞儀のチカラ」体験会
午後は、保護者と指導者の方も一緒に「お辞儀のチカラ」を学び合いました。
これまで800人以上の子どもたち、200人以上の大人たちに伝えてきましたが、何度やってもこれは面白い。
そして、バスケにも人生にも活きる重要なことが詰まっています。
一生使える学びを、バスケを通して伝えています。
頭で学んでメモを取って「いい話を聞いた」で終わる授業ではなく、
実際に、自分の身体で”検証”して、
自分の身体で感じて、仲間と一緒に学ぶ。
これが「活用」に至るための最も効率のいい学びであるし、一生残る記憶となります。
何よりも「楽しい」というのを
皆さん感じてもらえるのが僕も嬉しいです。
僕らはみんな、素晴らしい可能性を持っています。
生まれながらにして、
身体に素晴らしい可能性がある。
そのことを、指導者も、生徒も、保護者も感じてもらえて何よりです。
このワークをすると、
指導者が選手と関わる時、
保護者が子供と関わる時、
「自分の在り方」が変わります。
それが結果として、関わる人との関係性をより良くします。
相手を変えようとする前に、自分自身を変える。
自分自身を整えることで、
相手が変わり、日常が変わり、
人生が変わっていきます。
より良く、より楽しく、より豊かに。
「バスケットボールを通して人間力の向上を!」
というと、キレイゴトに聞こえたり、フワッとしていたり、
中には理想論だと言いたくなる人もいると思うのですが(昔の僕がそうでした)、
バスケと人生は、別々のものではありません。
同じ「ヒト」がやっていることですからね。
「学生の時に知っておきたかった」ということを伝えられたこと。
普段、子どもたちに関わる指導者と保護者の方が参加してくれたこと。
とても嬉しかったです。
ここでお伝えしていることは、
学校では学べない(仕組み上)し、
日本人の1%もまだ知らないことです。
なぜなら、武術の世界で「秘伝」とされてきたことだから。
じゃあ、何でそれが今の時代、公開されているのか?
それは、
・若者の自殺率が世界ワースト
・情報に溢れ、何が正解か分からない
・将来やりたいことがない子供が多い
・大人の世界が乱れて、子どもの世界が歪んでいる
・AIが発展している今、人間の感性を開く必要がある
だから、僕の師匠が秘伝を公開しました。
これは「誰かの教えの中に入る」というものではありません。
むしろ、その逆です。
「誰かの教えから離れて、自分で自分を創る」
多くの人は、誰かから言われたことを正解として鵜呑みにして、
最先端の情報、著名人が言っている凄いこと、一発逆転の方法論を求めています。
でも、本当の答えは「自分自身の中」にあります。
身体は様々なことを五感で感じています。
それは言葉にはできないものだったり、
自分の頭で考えるよりも先に受け取るものですが、
そういった「身体で受け取っていることや感じていること」が大切です。
鳥肌が立つような感動すること、自分の心が動かされること、自分が嫌だなと思うこと、自分が好きだなとおもうこと。
そういったことを損得や世間一般の良し悪しで判断するのではなく、
自分の身体で感じとって、ひらめきを行動に移していくことが人生創造ではとても重要です。
そんなことを「礼」の楽しいワークを通して伝えているのが「お辞儀のチカラ」になります。
今後も大和籠球では、
・「得たい成果」に合わせたバスケ指導
・一生使える「本物の礼」
を伝えていきます。
こういった直接指導で得られる学びを「オンラインコミュニティ」で体系化していきます。
大和籠球は、日々進化しています。
共に整え、共に進化していきましょう。
面白いバスケットボールを、更に面白く。
最後までお読みいただき、ありがとうございます!
PS.
直接指導の依頼は、こちらから。
大和籠球 勉強会(直接指導)
PS.
近々、「賢者は強者に優る」メルマガ講座を開始します。
SNSなどで告知していきますので、チェックしておいてください。
今後ともよろしくお願い致します!
PS.
勉強会の感想まとめ
◯氣付きが得られたところ
・礼を一度首を曲げずにやることでパフォーマンスが変わって良いプレーができるようになるということ
・礼は大事、礼をすることによって体を操れる
・礼とか言葉が少し違うだけで力の入り具合が全然違う
・礼をすることで気持ちが上がったり、姿勢が良くなったりする。プレーにも影響することがわかった(コミュニケーション)
・言葉が実際に動きにつながると知ることができた
・首と胸椎が体の支えや力の入れ具合を左右している
・声が大事だけどその言葉で変わる
・人との関わり方も大切、プレーに繋がる
・ポジティブ大事
・普段の礼やあいさつ、言葉が自分や相手に影響を及ぼすのを知った(首や胸)
・バスケにもつながっている(声を出す→流れをつくれる)
・バスケでできていないものは普段の生活の中でもできていない
・礼を意識するだけでそれが体にも出る、バスケにもつながっている
・言葉だけでも変わる
・礼をするときは首が大事
・ポジティブな言葉をいうと自分に返ってくる(相手の目は鏡)
・言葉→自分に返ってくる
・習慣が大事・いつも試合中にパスカットをもらえずにいたので、カットできるいい経験になりました
・今までDFの位置が違う(ドライブしないのにドライブコースにいる)
・パスは強く、はやく!
・DFの時の手をOFに影響がある手にする
・後ろからの声がけは名前を呼ぶ
・目線で予測を立てる
・バスケットボールの三間
・バスケが上手下手関係なく姿勢や意識をみんなでやることで気持ちが1つになる
・DFのポイント「ポジショニング、ビジョン、トーク」
◯今後活用できそうなところ
・毎日礼を綺麗に美しくやろうと思う
・コートに入る前の礼など、礼を意識する
・礼を1回ずつ意識する
・少しでもいいから1日1回は気にして礼をする
・コミュニケーションを取る時の言葉によって相手の気持ちも変わる、良い言葉をかける
・拍手の仕方
・礼で相手や自分に対する言葉を意識する(声が大切!)、1日の始まりが良くなり自分も相手も気持ちが良くなる
・コートに入る前の礼!チャレンジ精神!1日1回礼を意識!
・1日5秒の礼をする
・学校とかの日常でよい礼をして気持ちのよい生活→バスケにつながる
・普段、礼をする時や気合いを入れるときに丁寧にお辞儀をする!
・礼(学校のあいさつとかでも意識してみたい→良い生活→バスケにもつながる)・DFの時の手の出し方
・目線や体の向きで次を予測する
・ディナイの時の立ち位置を試合で生かせる
・DFの時にボールマンの動きを予測する
・ミスを恐れずチャレンジする
・ボールマンがシュートモーションに入った時にボールに触りにいく
◯もっと知りたいこと
・日々の生活でやっていることの秘密
・なんで日本人は礼をたくさんするのか
・礼をする意味
・言葉や鏡の意味をもっと知りたい
・猫背の正し方・シュートの打ち方
・速攻の走り方
・バックカット以外で簡単に点を取れるプレー
・OFで流れを止めずに動く方法
・3線のポジショニングとヘルプの出方
・余裕を持って攻める方法
・チームの流れが悪くなったとき、どのような声がけと雰囲気を作った方がいいのか
・相手の流れに乗られてしまった時、どうやって自分たちの流れをつくることができるのか
◯成長点・課題点
・ディナイを意識してパスカットができるようになったこと
・パス回しが速くなった
・次の動きを予測する
・パス回しが速くなった
・ディナイDFでパスカットできることが増えた
・1線の手の出し方を意識できた
・仲間にかける言葉を変えるだけでDFがスムーズになった
・DFの1線の間合いに気をつけることができた
・DFのスライドとかの時に足を閉じなくなった
・パスの強さ、速さ
・カッティングのタイミング
・DFは疲れる…としか思っていなかったけど、いいDFができたり、カットできたりすると楽しくなった!・礼とか言葉の影響力を知れた
・自分の気持ちが全体的に明るくなったところ
・小さなことでも気にしていけば変われる
◯課題点
・ディナイを意識しすぎるとバックカットをされてしまったこと
・パスを出すタイミングが悪い
・1対1やシュートができる場面でパスをしてしまう
・OFが止まった時の次の動き出しが遅い
・どうしても集中すると声が出なくなったり、ポジショニングを気にすることができなくなってしまった
・そっと周りを気遣い、行動できるようにする
◯感想
・今日はバックカットの知識以外に日常で使える「礼」や「相手」のことを教えてもらい、これから1日の始まりは教えてもらった「礼」をしようと思う。
・少し意識するだけで変わるんだなと改めて実感した。今日教えてもらったことをこれからの練習や試合で使えるようにする。礼に対する意識が変わった。
・今日はありがとうございました。前までの練習では無意識にやっていた手の出し方や「礼」や言葉の影響力を初めて知って驚きました。今後のプレーヤ生活に今回学んだことをしっかり生かしたいと思います。
・「基本」がどれだけ大切なのかということを1日を通してとても学べたので良かった1日でした。プレーでやりたいことは日常でも習慣づけることが大切だと知りました。今回学べたことを継続したいと思いました(大事!)
・今日はありがとうございました!とても楽しかったので、また来ていただけると嬉しいです!
・今までは全然、礼や言葉に対する興味や関心がなかったけど、今日の話を聞いて、効果を体で感じることができ、言葉や礼に対する意識が変わったし、興味が湧いた。これからも礼などを活用していきたい。
・自分がいままでしれなかったことを知ることができて、できなかったプレーなどができるようになってとても嬉しかったし、楽しかったです!それを今後も続けていこうと思います!
・みんなで声を出したりするとDFが楽しい!
・バスケの技術や気持ちのこととか、今まで知らない意識していなかったことをたくさん知れた。もっと技術面も教えてもらいたい。
・継続、行動に移すこと!
※保護者◯氣付きが得られたところ
・正しい姿勢、相手の目を見る、ポジティブな声がけ、どれも何気なく言われたり言っていることがこれだけ大きな効果や意味があることなんだと気づきました。
・姿勢、礼、言葉の使い方で発揮できる力とても変わる。
・ポジティブな言葉の強さ◯今後活用できそうなところ
・日常生活だけではなく会社の中でも活用したいと思います。
・普段からお辞儀、姿勢を正すこと
・気持ちの良い言葉をチョイスすること◯成長点・成果点
・改めて体験、体感してみることで実践してみようと思えたことが良かったです。
・5秒の習慣、私のようなズボラな人間でも変われる、人生を前向きに楽しく生きることができそう!◯課題点
・姿勢の悪さを直す!◯感想
・日本の武術などでも礼を大切にすることを重んじており、自分の子らにも何となくそういう心を教えたいと思っていましたが、何となくだったものがしっかりと理屈や背景まで含めて知ることができました。ありがとうございました。
・初めて知り得た事ばかりで、とても楽しく、それにより周りもHappyにすることができると思いました。
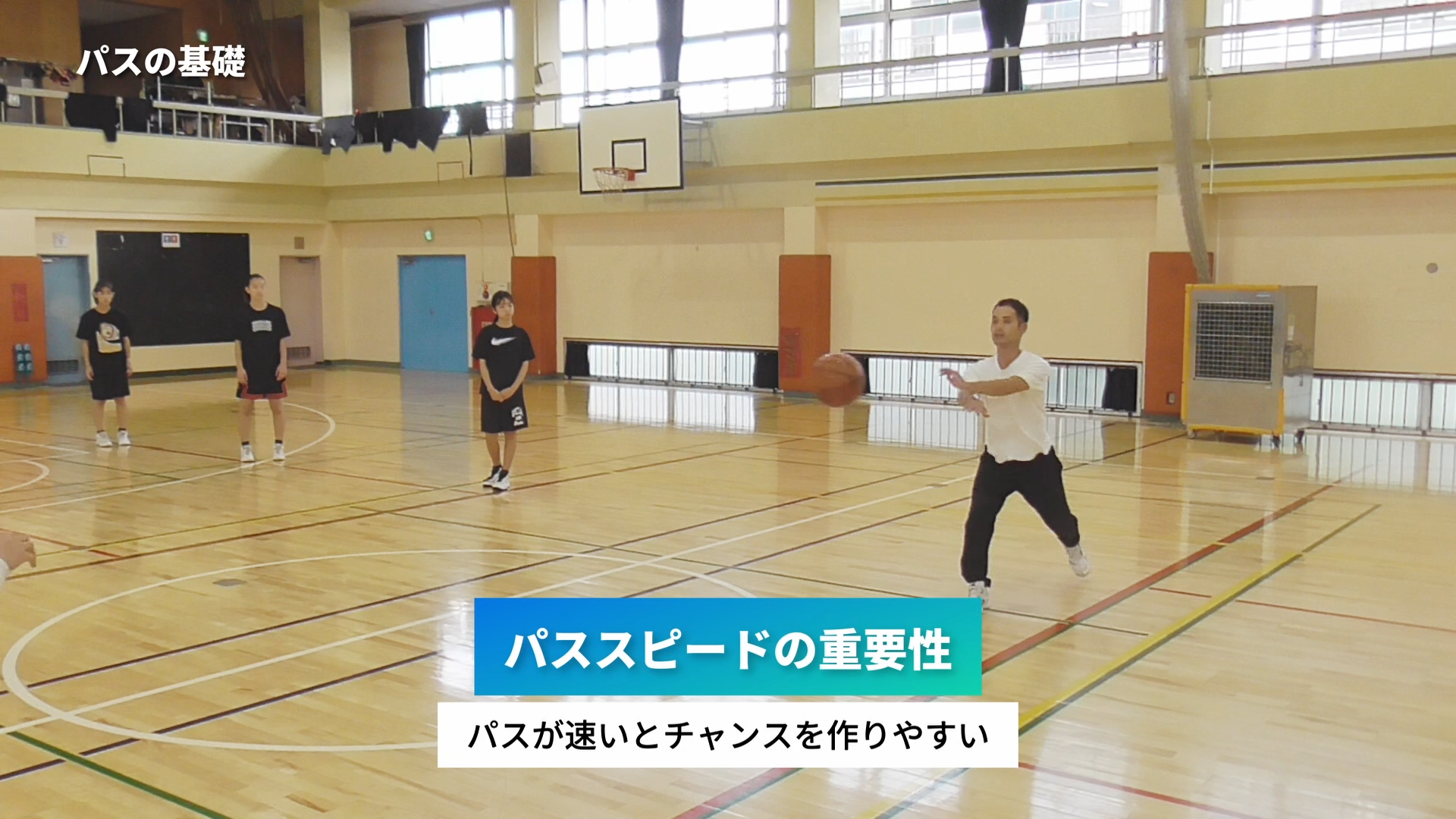























[…] る時にご覧ください。 U15女子チームでの指導「ディフェンス」「ファンダメンタル」「バックカット」 […]